目次
前編の振り返り
古代メソポタミアでの星の観察から始まり、ギリシア、イスラム圏、東洋へと広がった占星術。その歴史は、人が「自分を知りたい」と願ってきた歩みそのものでもありました。
第3章:占星術の成り立ち・基本構成要素
星・惑星・黄道12星座とは?
星座や惑星、そして黄道12星座は、占星術における言葉とも言える存在です。まず「黄道(ecliptic)」とは、地球から見た太陽の一年間の通り道を示す天空上の線であり、この線上を太陽・月・惑星がたどるため、古来「星と人・時間を結ぶ道」と考えられていました。
西洋占星術ではこの黄道が12の30度区分に分けられ、それぞれに星座の名が与えられています。具体的には、 牡羊座(Aries/3月21日-4月19日)から 魚座(Pisces/2月19日-3月20日)まで12あります。各星座には「元素(火・地・風・水)」「モダリティ(活動・不動・柔軟)」といった枠組みもあり、それによって性格・傾向を読み解く基盤が作られます。
惑星は、太陽・月・水星・金星・火星・木星・土星などがよく用いられ、それぞれが象徴的な意味(たとえば火星=行動・衝動、金星=愛・美)を帯びます。西洋占星術では「生まれた瞬間の天体配置(チャート)を読む」ことで、その人固有の地図が描かれるのです。
このように「星・惑星・星座」は、占星術が「宇宙と個人をつなぐ架け橋」として機能してきた構成要素であり、自分と時間・場所・宇宙の関係を静かに見つめるための出発点となります。
ハウス・アスペクト・惑星配置 — 体系の基礎
星と星座が「何を語るか」を示すなら、ハウスやアスペクトは「どこで・どのように語るか」を教えてくれます。
12のハウスは人生の領域を象徴し、1ハウス=自己、7ハウス=対人、10ハウス=社会的立場…というように人生の舞台を表します。出生時間と場所をもとに、どの惑星がどのハウスにあるかで、その人の経験テーマが読み取れるのです。
さらに、惑星同士がつくる角度(アスペクト)は相互作用を示し、協調や緊張、成長のきっかけを教えてくれます。(出典:British Museum – Ancient Astrology Collections)
第4章:代表的な占星術体系の紹介(西洋・インド・中国)
占星術には、主に、西洋占星術、インド(ヴェーダ)占星術、中国の占星体系の三つの体系があります。
この章では、上記の代表的な占星術について紹介します。
西洋占星術
西洋占星術(Western Astrology)は、古代ギリシャ・ローマに根ざし、天文学・哲学・神秘思想が交錯しながら発展してきた体系です。出生日時・場所をもとに「ホロスコープ(出生図)」を作成し、そこに配された惑星・星座・ハウス・アスペクトを読み解くことで、その人固有の「星の地図」を描き出します。
まず「太陽星座」はその人の基本的な生き方・目的を示し、一方で「月星座」「アセンダント(上昇点)」などが内面・外向きの表現・人生のスタイルを補完します。たとえば、ある人が太陽を牡羊座に持ち月を蟹座に持つとすれば、「行動的・自立志向(牡羊)」でありながら、「感受性・家庭志向(蟹)」という対照的な側面も併せ持つことが読み取れます。
さらに、西洋占星術では「惑星のトランジット(現在の動き)」「プログレッション(進行図)」「帰還図(サターンリターンなど)」といった時間の読み方も充実しており、人生の転機・成長・内的変化を星の動きというレンズで捉えることが可能です。心理占星術の潮流では、ホロスコープを「課題・潜在性・癒し」の視点から読むことが主流となってきています。
このように、西洋占星術は「個人の人生を星という物語で見る」ためのツールとして、現代ではセルフ理解・人間関係・キャリア・人生問いとして幅広く利用されています。
インド(ヴェーダ)
インドのヴェーダ占星術(Jyotish)は「光の知識」という意味を持ち、古代インドの聖典ヴェーダや天文学・暦学と深く結びついた体系です。この占星術の特徴は、単に出生時点の配置を見るだけではなく、「カルマ(行為・結果)」「輪廻(生まれ変わり)」「魂の学び」という哲学的な枠組みを前提にしていることです。
技法としては「ラグナ(上昇点)」「月ラグナ」「ナクシャトラ(星宿)」「ダシャ(大時期)」「ブクティ(小時期)」等が使われ、時間の流れ・人生のサイクル・魂の運びを読み解く縦軸・横軸を持ちます。また、西洋占星術が季節基準(トロピカル黄道)を用いるのに対して、インド占星術では恒星基準(サイデリアル黄道)を用いる流派もあり、星の読み方・チャートの構築において異なる視点があります。
実践的には、結婚・キャリア・健康・教育など人生のキーエリアに対して「いつ」「どのように」というタイミングを読むための枠組みが非常に明確で、個人の人生設計・修行・スピリチュアル成長の支援ツールとしても用いられています。
このように、ヴェーダ占星術は「魂・時間・運命」という大きな文脈を抱えながら、星を通じて人生を俯瞰するための知恵とも言えます。
中国の占星体系
二地支の六十年周期)といった体系を中心に発展してきました。たとえば、12の動物からなる十二支は12年でひとつの周期を示し、そこに五行が絡まることで60年のサイクルが形成されます。(出典:Tiny Rituals)
中国占星術では「年・月・日・時刻」を軸に命式(例:四柱推命)を立て、その中でその人の性質・運勢・時期を読むという手法が一般的です。(出典:feng-shui-institute.org)
また、星や惑星だけでなく「時間・社会・天(天体)・地(地理)・人(人間)」の調和を重視し、個人を宇宙・自然・社会の中で捉える視点が特徴的です。例えば「この年の十二支と五行の組み合わせ」「月や時刻の支・干の影響」「天干・地支の相関」など複雑な読みが行われます。(出典:Palos Verdes Pulse)
このように、中国の占星体系は「個人」だけでなく「時代・社会・家系・流れ」を包括的に捉える知恵と言え、西洋・インドとはまた異なる視座を提示してくれます。
第5章:占星術の現代的な展開・国内外の比較
現代における占星術の使われ方(新聞・ウェブ・アプリ)
今日、占星術は新聞の12星座占いからスマホアプリ、SNSでの「星読み投稿」まで、さまざまな形で日常に溶け込んでいます。
星占いが単なる「運勢」ではなく、「自己理解」や「タイミングを知るためのガイド」として受け止められるようになったことが、現代的な変化の一つです。
特にZ世代以降では、占星術を“メンタルケア”や“セルフリフレクション”の一環として用いる流れも見られます。(出典:The Conversation – Why Astrology is Making a Comeback)
海外(欧米/インド)での受容と日本での受容の違い
欧米では、占星術は心理学や自己啓発と結びつき、「自分を知る科学」としての側面を強めています。インドでは今も社会や家庭の意思決定に用いられる実用的な学問であり、出生時の星配置が結婚・仕事・健康に影響すると信じられています。
一方、日本では、星座占いが“気軽な楽しみ”として定着しており、文化的に柔らかく取り入れられてきました。
この違いは、宗教観や社会構造だけでなく、「個人」と「宇宙」の関係をどう捉えるかという哲学の違いでもあります。(出典:BBC – The Global Rise of Astrology)
批判・科学的視点・注意点
占星術は長い歴史を持つ一方、科学的には「因果関係を立証できない」として批判も受けています。
しかし近年では、「星は象徴の言語であり、自己理解を促す心理ツールである」という解釈が広がっています。
重要なのは、占星術を「絶対の答え」ではなく「自分を見つめるための鏡」として用いること。科学と神秘の間に立ちながら、占星術を“人間の内的宇宙を探る試み”として見つめる視点が求められています。(出典:Skeptical Inquirer – The Science of Astrology)
第6章:読み手へのメッセージ/活用のヒント
「楽しむ」ための占星術活用法
占星術は、未来を当てるものではなく、“今を感じるための手段”です。
自分の星座を知り、毎月の天体の動きを意識するだけでも、感情や出来事の流れを穏やかに受け止められるようになります。
「星を味方につける」とは、星に頼ることではなく、自分と世界をやさしく調和させることなのです。
批判的視点を持つためのチェックポイント
- 占星術は「視点のひとつ」であり「答え」ではない
- 星の象徴を、現実の文脈に照らして受け止める
- 星を使って「自分を責めない」「他人を判断しない」
これらを意識すれば、星はあなたの自由を奪うものではなく、支える存在になります。
「逃避日和」に生きるための活かし方
「逃避日和」が大切にしているのは、“生きるを楽にする知恵”。
占星術もまた、あなたの人生に「小さな余白」を与えてくれるツールです。
星を読む時間は、現実から少し距離を置き、心を整えるための“やさしい逃避”でもあります。
星を通して、自分を知り、受け入れ、多少のことは受け流して笑って生きていける——。そんな日々の支えとなれば嬉しいです。


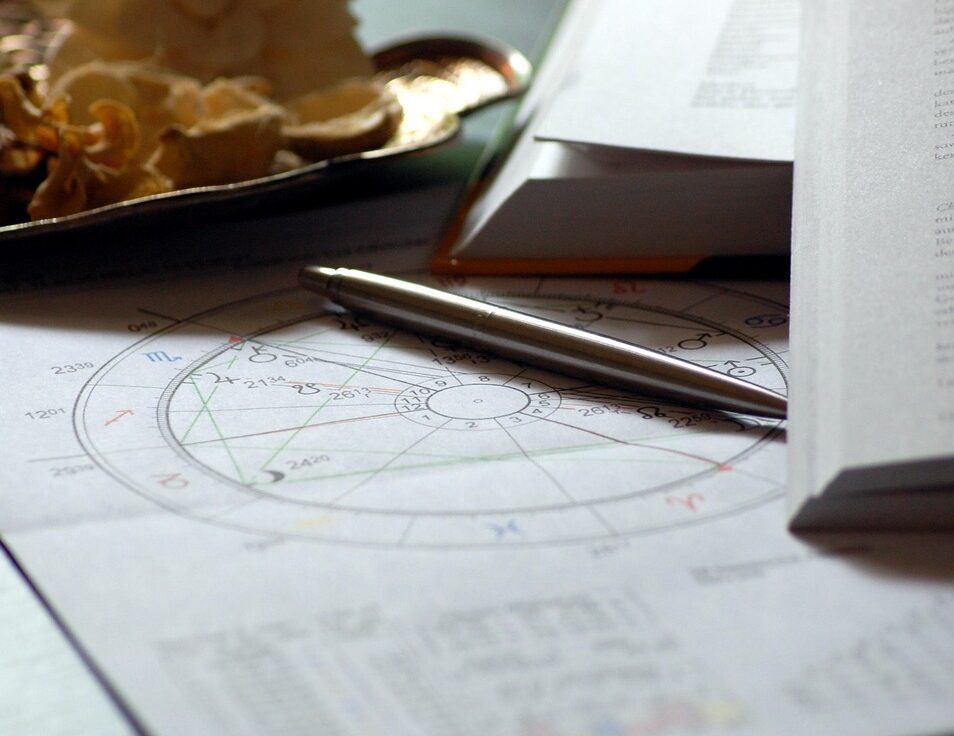
コメントを残す